日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。
日本の子供たちが、英語を身につけて ミライに羽ばたくために。
2025.09.24
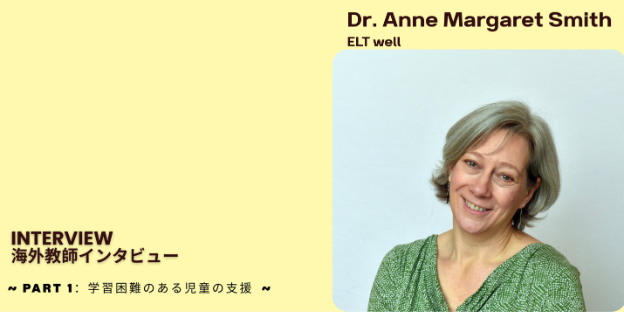
Anne Margaret Smith(アン・マーガレット・スミス)博士は、ケニア、ドイツ、スウェーデン、ニュージーランド、イギリスなど複数の国にわたって、30年以上のEAL(追加言語として英語)指導経験を持つ著名な教育者です。また、ニューロダイバーシティ(神経多様性)の専門家でもあります。
特別な教育ニーズを持つ言語学習者を支援するため、教育者が理解を深め、実践的な戦略を身につけられるよう手助けしています。Anne Margaret博士の著書や講座は多くの人々に影響を与えてきており、本記事の著者もその一人です。
ますます多様化が進む現代の教育現場では、さまざまな学習プロファイルを持つ子どもたちをどのように支援すべきかを知ることは不可欠です。この点こそが、今回のインタビューの主なテーマです。Anne Margaret博士による、生徒たちに寄り添った包括的(ホリスティック)なアプローチは、地域社会におけるニューロダイバーシティをより深く理解し、支援し、尊重したいと考える教育者や保護者にとって、実践的な指針となるでしょう。
取材・著者:Paul Jacobs
翻訳:Yuri Sato
まとめ
● ニューロダイバーシティは、ディスレクシア(発達性読み書き障害)、DLD(発達性言語障害)、ADHD (注意欠如・多動性障害)、自閉症を網羅し、それらが相互につながっているスぺクトラム(連続体)として捉えることができる。こうした捉え方によって、より正確なアセスメントとサポートを提供できるようになる。
● リズムと音韻に注目した音楽中心のアクティビティを取り入れることで、ニューロダイバースな(神経発達に多様性のある)学習者の音韻認識能力と読み書きの発達をサポートすることができる。
● 第二言語の学習は、認知能力を強化することができる。そして、たとえ小さな進歩であっても、新しい言語の習得は生徒の自尊心を育むことができる。
Q:これまでのご経歴や現在の役割に至るまでの経緯について、少しお聞かせいただけますか?
私は言語聴覚士(Speech and Language Therapist)です。現在、メンタルヘルスの問題を抱える自閉症の成人を支援しています。イギリスの国民保健サービス(NHS)における私の役割は、コミュニケーションの違いを特定し、患者とメンタルヘルス医療スタッフ間のコミュニケーションを円滑にすることです。
また、「ELT Well」 という自分の会社も経営していまして、神経発達状態と言語学習に関する知識の普及に力を入れています。さらに、ディスレクシアのアセスメント(評価)も行っています。
もともとは言語聴覚士になるつもりで、大学で言語学を学んでいたのですが、途中で英語教育の分野へ方向転換しました。英語の指導は楽しかったのですが、周りと同じペースで学習できていない生徒たちがいることに気づきました。当時、教育制度が優れた国として知られるスウェーデンで教えていましたが、どういうわけか、このような生徒たちは自分の言語で読んだり書いたりすることができないまま学校を卒業していたんです。
この経験をきっかけに、私は読み書きの発達についてさらに学びまして、ディスレクシアのアセッサー(ディスレクシアの評価を行う専門家)になりました。さまざまなニューロタイプ(神経発達のタイプ)について調べ続けるうちに、ディスレクシアやディスプラクシア(発達性協調運動障害)などのカテゴリーは重複することが多いと気づきました。私たちは往々にして、より包括的なアプローチをとるのではなく、厳格なカテゴリーに分類しようとしてしまいます。
Q:先生は、長年にわたってニューロダイバーシティと言語学習に対する認識を広めてこられました。そして、一部の生徒が言語の発達に遅れや困難を抱えていることに気づいたとのことです。このような課題があるなか、なぜ、こうした生徒たちにとって二つ目の言語を学ぶことが有益だとお考えなのでしょうか?
別の言語を学ぶことは、私たちに数多くのメリットをもたらしてくれます。脳内で神経のつながりを増やすので、認知能力の発達に良い影響を与えます。また、社会的には、別の視点から物事を見るようになります。さらに、自尊心も高まります。別の言語を使って誰かに挨拶をする、というちょっとしたことをマスターしただけでも、ものすごく大きな達成感を得ることができます。研究によると、高齢になってからの認知機能低下を防ぐ要因になる可能性さえあります。
さらに、別の言語を学ぶことは、一つ目の言語をよりよく理解することにもつながります。私が生徒 だったときは、英語の文法をはっきりと説明されて学んだことはありませんでした。英語の文法をちゃんと理解できたのは、フランス語とドイツ語を勉強したおかげです。その経験は、のちに、よりよい教師になるための助けにもなりました。
複数の言語を話す人は、一つの言語しか話さないモノリンガルにない強みや能力を持っている可能性があります。
Q:別々のニューロタイプがいくつも重なり合ったり、お互いに関連し合ったりしていることに気づいた、というお話がありました。どのようなことかもう少し深く理解したいのですが、教えていただけますか?そのようなニューロタイプとは何であり、それらはお互いにどのように関連しているのでしょうか?
ニューロダイバーシティとは、人間の脳にはさまざまな違いがあることを表すための包括的な用語です。ニューロダイバーシティの中で、こうした違いをいくつかの「ニューロタイプ」に分類しています。学び方の違いや学習障害は、最も一般的な例です。例えば、ディスレクシアはとてもよく知られているニューロタイプです。表面的には、ディスレクシアは読み書きにおける困難として現れますが、情報の記憶や処理速度、整理、そして音韻処理能力や音韻認識能力にも影響を及ぼします。ディスレクシアの人は、ほかのニューロタイプの特性を示すことが多いです。例えば、空間認識、協調、動作の順序づけ、バランス、リズムなどに関わるディスプラクシアなどです。もう一つのニューロタイプは、ディスカリキュリア(算数障害)です。これは、数の概念や数列の理解に影響を及ぼします。これは、ディスレクシアにも見られる特性です。
自閉症やADHD も、ニューロダイバーシティ群の一部であり、よく知られています。実は、「ニューロダイバース(神経発達に多様性のある)」という用語は、自閉症のコミュニティで生まれたものです。自閉症と ADHD は、主として学び方の違いではないため、ディスレクシアと同じカテゴリーに分類すべきではない、という意見もあります。このディスレクシアは学び方の違いであるのに対し、自閉症は生活全般にわたる違いである、と言うかもしれません。この見解も理解できるのですが、私はどちらかといえば、そうは思いません。学び方の違いがその人の生活全般に大きな影響を与えるのと同様に、自閉症やADHDも学習に重要な影響を与えます。
とはいえ、自閉症の人とディスレクシアの人には、コミュニケーションにおいてはっきりとした違いがあります。例えば、自閉症の人たちは、ことばをより文字通り解釈することが多いです。また、ほかの人たちと関わり合うときに、雑談や社交辞令はあまり必要ないとみなして、目的を達成するため、あるいは必要なときに限ってやりとりしようとする場合があります。
ADHD の人は、集中力や注意力を維持したり、感情をコントロールしたりすることが非常に難しい場合があります。感情の起伏が激しいように見えることがあり、これは自閉症とも多少共通します。
最近では、言語聴覚士として、ディスレクシアと密接に関連するDLD(発達性言語障害)の研究に取り組んでいます。実際、DLDはよくディスレクシアと誤認されます。DLDは、音韻、意味的なつながり、構文の発達など、言語のあらゆる側面に影響を与えます。
これらすべてのニューロタイプに共通していることは、記憶と情報の処理方法です。情報をどのように理解し、保持し、取り出すか、ということですね。大きな課題となるのは、多くの場合、自尊心です。周りの世界を違うふうに処理するので、実際には仲間たちよりも努力しているかもしれないのに、みんなと同じ成果を上げるのに苦戦して、疎外感や挫折感を抱くことがあるからです。
Q:お話しいただいたさまざまなニューロタイプには、共通する特性がたくさんありますが、アセッサーとして、このようなタイプをどのように正確に見分けているのでしょうか?
良いご質問ですね。私はイギリスを拠点としていますが、イギリスでのアセスメント体制は、かなり区分化されています。例えば、ディスレクシアのアセッサーである私は、正式にディスプラクシアを診断することはできません。この診断は、作業療法士や小児科医が行うものです。ただ、ディスレクシアのアセスメントを行うときに、特徴がディスプラクシアに似ていると気づいたら、正式に診断することはできませんが、その観察内容を報告書に書きます。
同様に、自閉症や ADHDも医学的な症状とみなされるため 、医師が正式な診断を下す必要があります。ディスレクシアのアセスメント中に自閉症やADHDの兆候であるを特性に気づいた場合は、それらを気になる点として指摘して、さらに詳しい評価を受けるよう本人に勧めます。
言語聴覚士である私は、その職務の一環として、DLD(発達性言語障害)は正式に特定することができます。でも、人によっては、アセスメントのプロセスが大変な場合があります。特に、4時間にわたるディスレクシアのアセスメントを終えたばかりなのに、自閉症のアセスメントなど、さらなる評価のために別の専門家に紹介されることになった人たちは大変です。
Q:アセスメントを通じてディスレクシアを特定する際、どのような兆候に注目しますか?
通常、私たちはまず、その人の読み書き能力がどのように発達してきたかを調べます。例えば、学校教育を受けてきたにもにもかかわらず、読み書き能力が思うように伸びない場合、それはディスレクシアの兆候である可能性があります。ただし、これは単に初期段階の表面的な段階に過ぎません。そこからさらに深く掘り下げて調べる必要があります。読み書き能力が通常のように発達しない場合、その主な理由の一つは、音韻認識能力に関係していて、ワーキングメモリや処理速度の影響を受けることがあります。
私は、英語を追加言語として話す人たちに対してアセスメントを行うことがよくあるのですが、その中には、学校教育をまったく受けてこなかった人もいます。紛争によって混乱が生じた社会で育ち、日常的に学校に通うことができなかった人たちです。あるいは、女性が男性と平等に教育を受けることができなかった文化圏で育った人たちもいます。特にこのようなケースでは、表面的な読み書きの能力だけにとどまらず、音韻処理能力、情報処理速度、思考の整理方法など、もっと深く掘り下げた側面も見ていきます。
日常生活からの観察も、良い手がかりになります。例えば先週、ある女性の方のアセスメントを行ったのですが、その方の息子さんがコミュニケーションのサポートのために同席していました。息子さんは、母親が料理をしているときに、塩を入れたことを忘れてまた塩を入れてしまうことがたまにあります、と話してくれました。このような体験は、ワーキングメモリに問題があることを示しているかもしれません。これも、ディスレクシアによく見られる特性です。アセスメントの目的は、その人全体を観察することです。
その人の弱みを特定するだけでなく、強みを発見することも同じくらい必要です。記憶や音韻認識、処理速度に加え、協調、細かい動作のコントロール、手と目の協調も観察します。これらは通常、ディスプラクシアと関連性が高いですが、異なるニューロタイプ間にはかなり多くの共通点があります。ほかのニューロタイプに関連する特性に気づくことは、全体的なアセスメントを確かめやすくなります。さらに、ニューロダイバーシティは遺伝する傾向があるため、私たちは家族歴についても考えます。
良い面としては、アセスメントを受けることによって、学校や職場に自分のニーズをはっきりと伝え、ほかの人たちよりもタスクを終わらせるのに時間がかかる理由を説明しやすくなります。また、自分と同じように思考する人たちとつながることができ、健全な自尊心とコミュニティ意識を育むことができます。
後編では、特に学習上の困難を抱える人たちの言語習得にとって、音楽がどのように役立つツールであるかということについて、お話を伺います。
【取材協力】
Anne Margaret Smith(アン・マーガレット・スミス)博士(ELT Well)

<プロフィール>
ケニア、ドイツ、スウェーデン、ニュージーランド、イギリスなど複数の国にわたって、30年以上のEAL(追加言語として英語)指導経験を持つ著名な教育者。また、ニューロダイバーシティ(神経多様性)の専門家でもある。ランカスター大学で教育学研究・言語学の博士号を取得し、語学教師養成におけるインクルーシブ教育について幅広く研究。2005年には「ELT Well」を設立。ニューロダイバージェントな(神経多様性のある)言語学習者を効果的にサポートすること、そして、そうした学習者をより深く理解してサポートできる教育者の養成を手助けすることを目的とした団体である。生涯にわたって音楽への熱い思いをもち続けてきたAnne Margaret博士。その情熱を原動力として、音楽的な要素を言語活動に取り入れ、学び方に違いのある生徒たちがより効果的に能力を伸ばせるようサポートしている。また、長年、ディスレクシア(発達性読み書き障害)のアセッサーとして活動してきた。現在は、ASD(自閉スペクトラム症)の成人向けサポートを専門とした有資格の言語聴覚士(Speech and Language Therapist)としても活動する。
■関連記事
学習困難のある子どもが外国語を学びやすいようにするサポート方法とは?〜Judit Kormos教授インタビュー(前編)〜
Evens, M. & Smith, A.M.(2019) Language Learning and Musical Activities. ELT Well
Smith, A.M.(2017) Raising Awareness of SpLDs.ELT well
Gordon, R. L., Fehd, H. M., & McCandliss, B. D. (2015). Does Music Training Enhance Literacy Skills? A Meta-Analysis. Frontiers in Psychology, 6.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01777
Overy, K. (2003). Dyslexia and Music. Annals of the New York Academy of Sciences, 999(1), 497–505.
https://doi.org/10.1196/annals.1284.060
Rathcke, T., & Lin, C.-Y. (2021). Towards a Comprehensive Account of Rhythm Processing Issues in Developmental Dyslexia. Brain Sciences, 11(10), Article 10.
https://doi.org/10.3390/brainsci11101303
Stanovich, K. E. (1988). Explaining the Differences Between the Dyslexic and the Garden-Variety Poor Reader: The Phonological-Core Variable-Difference Model. Journal of Learning Disabilities, 21(10).
Vellutino, F. R. (1981). Dyslexia: Theory and Research (Illustrated edition). MIT Press.